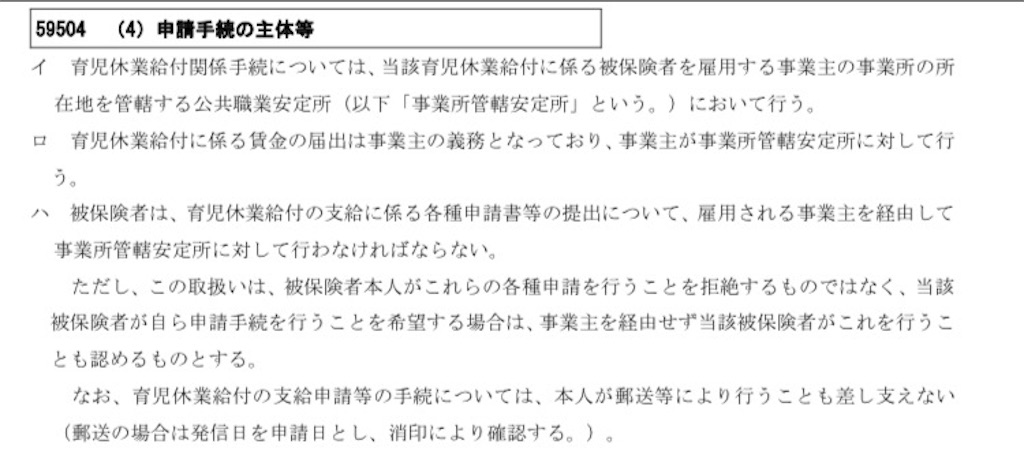育休延長厳格化後も保育園の申込みで育休延長も許容できるにチェックして問題ない理由
このブログのほかの育休延長厳格化に関する記事を読んだ方には何も得るところがない記事です。
さて来年春から雇用保険の育児休業給付を子どもが一歳を超えてももらうための手続が厳格化されます。一歳からの延長手続は4月より前に終わる方も一歳半の時に再延長で同様に厳格化の対象となることもあります。
何の書類が必要なのかは
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降) |厚生労働省のhttps://www.mhlw.go.jp/content/001270806.pdfを見てください。
ここでは認可園の利用申込の時に育休延長でも許容できる旨のチェック欄にチェックをいれると、どうなるのか、なぜそんなことになったのかを説明したいと思います。
そもそも育休延長のチェックとは何かというと、これは認可保育園の利用申込手続において、その保育園の各学年の定員を上回る申込があった場合に誰を入園させて誰をさせないのかを自治体が決めるのを利用調整というのですが、この利用調整の際に育休延長してもいいので、入園の優先順位を通常より低く取り扱ってくださいという意思表示をするためのチェック項目のことを言います。
もともと育休は育児休業給付も含め1歳ですっぱり終わる仕組みで育休延長チェックなどない世界だったのですが、平成17年から一回だけ延長して1歳半まで平成29年に2歳まで延長できるようになりました。休業前の給与に対する給付率もどんどん引き上がっていきました。
こうなった理由はもちろん待機児童となって離職することを防ぐためですが、給付としてはどんどんうまみのあるものになっていきました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001148652.pdf
給付が生活を維持できるレベルになるにつれ、そもそも本来の一歳ではなくもっと長く育休を取りたい人が増えてきました。一方で大半の人は確実に復職したいので保育園の整備を求め、長く育休を取りたい人でも入園できてしまう状況になりました。平成17年から育休給付を延長できる要件はほぼ保育園保留の一択であり、あとは養育者に不幸があるなど気軽に選択できるものではありません。
そうするとどうなるのかというと、保育園の利用申請に落としてくださいという嘆願書を添えるのが流行ったり、それでも受かると役所でカスハラを行ったり、4月の比較的入園枠が余りやすい時期に敗者復活戦的に行う二次利用調整に一次で受かったにも関わらず一度辞退して再申込して落選を狙うといったモラルの崩壊が全国的に発生したようです。
それで当時保育園の制度を管轄していた厚生労働省は平成31年に全国の利用調整をする市町村に通知を出しました。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_210_1.pdf
内容は2点、①利用申込書に育休延長のチェック欄を設けるとこういう混乱を避ける工夫になるよ②一次をわざと辞退して二次で保留になった人の保留通知には、一次を辞退してると書いてくれれば、これが書いてある人はハローワークが給付延長を認めない場合もあるよと厚生労働省も牽制するよ。ということです。
この時、通知では
直ちに復職希望と育休延長を許容できるの2択にして選ばせろと書いてありました。
これは強制的に導入を求める通知ではなくあくまで工夫の情報提供という感じでしたが、横浜市は育休延長許容チェックについてはほぼこの言葉どおりに導入しました。
ただこの許容チェック、これまでの制度悪用の実態を知らない人から見ると、絶対に延長できないわけではない…くらいの意味で優先順位が下がることに気づかずにチェックをしてしまう人もいます。まともな人は利用したいから利用申込を出すものだと考えていますから、そのくらいの感覚でチェックするのは良識的ですらあります。
なので、このチェックはもっと露骨な言葉に変えている自治体もあります。例えば2024年前半の世田谷区などは、育児休業の延長を希望するにチェックする形になっています。(2024.9.29追記 世田谷区の申請書は9月から申請書が「許容できる」になっていました。4月以降は「希望する」だとアウトですものね。)
しかし、待機児童の解消がさらに進むと優先順位を下げたところで定員割れで入園できてしまうので、待機児童問題が解消している自治体ではカスハラなどが再発してしまったようで、令和5年、一部の自治体からはそもそも保留を要件とする雇用保険の手続に問題があるのではないかという提言がされました。
結論としては、ハローワークの方で審査を厳格化してカスハラなどへの牽制効果を狙う案が厚生労働省から雇用保険を管轄する諮問機関に提示されそれで決まりました。
厳格化の対象はもちろん復職する気がないのに保留通知目当てで保育園に申し込む層です。
そういう意味では育休延長チェックは厳格化対象炙り出しのように見えてしまうのですが、しかし、これを徹底的にやると誰も育休延長チェックを利用しないので、時代は戦国時代に戻ってしまいます。そこで育休延長許容チェックの有無については今回公式的に厳格化の対象にしないことにしています。
第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|資料|厚生労働省
資料1-2のPDF7枚目赤枠一番下参照
また厚労省のマニュアル11ページにも同じことが書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001270806.pdf

念のため、入所保留を希望している、という言葉遣いだと延長の対象にはなりません。許容ならセーフ。厚生労働省の高貴な言葉遊びだと思って理解するのは諦めて機械的に判断してください。
詳細はわからないのですが、こども家庭庁は保留を希望するような言葉遣いを避けるよう前記の平成31年の通知を今年4月に改正したようです。
これを受けて北区などでは育休延長希望に関する申請書の言葉や提出書類名を変更する対応がとられているようです。
多分ここまで丁寧に説明してくれている自治体はなかなかないと思うのですが、まともな責任回避能力のある自治体ならハローワークから却下されるようなリスクのある様式は改正するでしょう。
2024.10.11追記 横浜市は様式にここにチェックしても給付延長の審査にはただちに影響ありませんと、チェック欄のすぐ下に書いています。ただちに、とか要らないですけど(後から影響でるんかい、となって書いた意味ないですよね。)英断だと思います。
今回の厳格化の言葉遊び感にはうんざりしますが、基本的に育休延長については気にせずチェックして大丈夫なのです。通勤途上にない遠方を単願で希望しなければよいだけです。
2024.8.23追記
ただし、延長チェックが横浜市のように利用申込と一体化している場合、延長にチェックを入れた利用申込などのコピーを会社に提出する必要が出てくるケースが多いかと思います。
会社の立場から言うと、復職するのであれば、会社は仕事やポジションを用意しておく必要があるので、延長する気になったらその時点で用意の必要がないことを知っておきたいところです。たとえ単に復帰したくないだけであっても、適当な方便を駆使して、しばらく自宅で保育していく方針を伝えるのが良いでしょう。例えば子どもの健康面で心配なことがあり、保育園生活をはじめるのが早いように判断している、延長がかなうなら延長したいといった感じです。
また、そもそも休業は延長しなくてもはじめから一歳以上認められる制度の会社もそこそこあるでしょうから、そういう会社は休業期間があらかじめ延長後の休業期間の承認を受けていればチェックの有無などどうでも良いはずです。
しかし死ぬほど面倒くさい人事がいる職場がこの世にないわけではありませんから、できれば自治体には希望園などを記載する利用申込と育休延長チェックの用紙は分けて、職場に提出しなくても良いようにしていただきたいものです。ハローワークはそこでは判断しないと言っているわけですから提出の有無を教えろとは言えないはずですし、職場に見せたくないから育休延長チェックをしないという面倒な人間が育休延長に失敗して、トラブルに巻き込まれるのはおそらく自治体ですし、1番割を食うのは延長失敗した人のために保留決定された速やかな復職を願うほかの保護者なのですから…。
一応業務取扱要領には、雇用主を通さず直接手続可能と書いてあるので貼り付けておきますね。どうしても会社にバレたくない方はハローワークに業務取扱要領の14ページ目にはこう書いてありますけど、どうですか、自分の所管のハローワークはどこですか?と訊ねたら良いと思います。